第1814回例会(2025.4.22)を開催しました
松戸西ロータリークラブ 第1814回 例会 令和7年4月22日
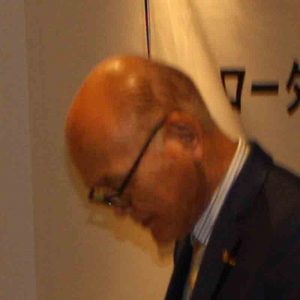
司会進行 石井 弘会員
天鐘 山本 衛会長

お客様紹介 加藤特許事務所 弁理士 加藤 祐一様

食事

会長挨拶 山本 衛会長
皆さん、こんにちは。先週のバーベキュー例会は、お疲れ様でした。初めてにも関わらず、皆様、多くの仕事を引き受けて下さり、ありがとうございました。初めての事が多かったので至らぬ点も多々あったかもしれませんが、どうかお許し願います。
さて、本日は、加藤祐一さんによる、外部卓話です。内容は、「個人と企業のブランディング入門」です。加藤さん、後ほど、よろしくお願いします。
さて、次週の4月29日は、杉山年度へ向けて、地区研修・協議会です。地区研修協議会をロータリーハンドブックにて調べますと、地区研修協議会は、必要な技能、知識、および意欲を持つクラブのリーダーを育成し、会員基盤を維持、および拡大し、それぞれの地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズを取り組むプロジェクトを実施して成功させて、プログラムへの参加と、資金寄付を通じて、TRF(国際ロータリー財団ですね。)を支援するために、なるべく3月4月5月のいずれかの月に、毎年開催されるものとする。ガバナーエレクトが、地区研修、協議会を計画、実施、指揮、監督するものとする。地区研修・協議会に出席を要請されるのは、次期クラブ会長と、クラブリーダーを含めるものとする。と、ありました。
地区研修協議会の目的 として、
就任に先立ち、次期クラブ指導者が、クラブの指導者チームを築けるようにする。地区ガバナーエレクト、次期ガバナー補佐、地区委員会にクラブ指導者チームの意欲を喚起し、協力関係を築けるようにする。
地区研修協議会の出席 として、
次年度ロータリー年度に重要な指導的役割を務めるクラブ会長エレクトから任命されたクラブ会員は、任命を受諾する前に、地区研修協議会への出席を約束するよう所属クラブに義務づけられるべきである。
と、ありました。いろいろとありますが、次年度杉山会長年度に向けて、地区のガバナーエレクトをはじめ、次期委員会の研修を受けることが大事なことのようです。次年度は、杉山会長のもと、40周年事業、石井ガバナー補佐の輩出、と行事が続きます。4月29日の地区研修協議会は、次年度に向けてのスタート地点と言っても、過言ではないと思います。お忙しいところ恐れ入りますが、どうか、地区研修協議会への参加をお願いする次第です。以上、会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告 河合 直志幹事
松戸中央RC様より 例会臨時変更のお知らせ
国際ロータリー ロータリーアットクラブよりお知らせ
コーディネーターNEWS
ハイライトよねやま
ロータリー希望の会奨学金より 風の便り
ロータリー財団委員長より MCRレポートより寄付状況のお知らせ
第13グループゴルフ大会 景品協賛の御依頼

外部卓話
「企業と個人のブランディング戦略入門」
—成功するための商標とセルフブランディングの違いと実践法—
弁理士 加藤祐一 様
皆さま、こんにちは。弁理士の加藤祐一と申します。 私は2007年に弁理士登録をし、これまで主に化学・材料分野を専門として、特許実務に携わってまいりました。2004年から、弁理士試験の勉強を進めながら、特許事務所に勤務し、特許庁に提出する明細書や意見書、補正書といった書類の作成を中心に、約15年以上、実務経験を積んできました。 ところが昨年、体調を崩したことをきっかけに、それまで勤めていた事務所を退職し、現在は自宅を拠点に個人事務所を立ち上げ、業務を継続しています。 近年、ChatGPTなどの生成AIの登場により、弁理士業務にも大きな変化が生じています。特許調査や明細書のドラフト作成といった業務の一部は、すでにAIによって効率化されつつあります。 このまま技術が進化すれば、5年後には「英語力」や「交渉力」「企画提案力」などのスキルを兼ね備えた“スーパーマン弁理士”しか生き残れない時代が来るのではないか…そういった危機感を抱いています。 そのため現在は、これまでに得た法律・知財の知識を整理し、コンテンツとして発信する活動にも取り組んでいます。制度をわかりやすく解説したり、実務での気づきを共有したりと、情報の伝え方にも工夫を加えています。 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
本日は「企業」と「個人」それぞれにとってのブランディングの重要性、そして「商標ブランディング」と「セルフブランディング」という2つの視点から、その違いと実践方法についてお話しさせていただきます。
第1章:なぜ今、ブランディングが重要なのか
現代のビジネス環境では、大企業だけでなく、中小企業や個人事業主も「ブランド」を意識しなければならない時代です。 なぜなら、インターネットやSNSの発展によって、私たちは常に「選ばれる立場」にいるからです。
似たような商品・サービスがあふれる中で、どれを選ぶか――その判断軸の一つが「ブランド」です。 ブランドとは、単なる名称やロゴではありません。ブランドには信頼感、安心感、世界観といった“目に見えない価値”が宿ります。そしてその価値を「意図的に」作っていくのが、ブランディング戦略なのです。
第2章:商標ブランディングとは何か?
まず、「商標ブランディング」についてお話しします。 これは簡単に言うと、商品やサービスの名前、ロゴ、スローガンなどを通じて「企業」としての信頼を築いていく手法です。 たとえば、「コカ・コーラ」や「ユニクロ」のロゴを見ただけで、品質や雰囲気をイメージできますよね? これがブランドの力です。 中小企業でも、名称やロゴを商標登録することで、模倣を防ぐだけでなく、「この会社はしっかりしているな」という印象を与えることができます。 また、商標法に法的保護を得ることにより、ビジネスの安定性も高まります。 特に最近では、ネットショップを開業する人が増えていますが、その中で「似たような商品名を勝手に使われた」といったトラブルも少なくありません。 これに備える意味でも、商標登録は「守り」でありながら、「攻め」にもなる重要なブランディング施策です。
第3章:商標ブランディングを進めるステップ
では、商標ブランディングを進める時には、具体的に何をすればいいのか? ここでは基本的な3ステップを紹介します。
1つ目は、ブランド名の選定。 ユニークで、覚えやすく、かつ他人の権利を侵害しない名前を選ぶ必要があります。
2つ目は、ロゴやビジュアルの設計。 たとえば、色やフォント、デザインの一貫性は、ブランドの印象を大きく左右します。
3つ目は、商標の出願と登録。
専門家に依頼してもよいですし、自ら出願することも可能です。出願から登録までは数ヶ月かかることが予想されますが、一度登録しておけば将来的なリスクを大きく減らせます。 これらのステップをしっかり踏むことで、競合との差別化ができ、信頼のあるブランドを築く土台ができます。
第4章:商標ブランディングのデメリット・リスク
商標ブランディングは強力な武器になりますが、万能ではありません。以下のような注意点があります。 柔軟性の欠如:商標は一度登録すると変更が難しく、ブランド名の変更には再出願や再周知の手間・コストが発生します。
法的リスク:他人の権利を侵害してしまうリスクや、模倣・係争の対象となるリスクがあります。
コスト:出願費用、登録料、更新料などがかかります。
共感性の低さ:商標は記号的であるため、顧客との感情的なつながりが築きにくい場合がありま
す。
拡張性:他者に運用を任せられる反面、品質低下や方針のズレが発生するリスクがあります。
継続性:法的に保護されているため、ブランドは長期に維持可能ですが管理の手間が生じます。
初動の信頼構築:ロゴや名前だけでは信頼を得るまでに時間がかかる傾向があります。
第5章:セルフブランディングとは?
セルフブランディングとは、個人のスキル、経験、価値観を外部に発信し、信頼と影響力を得ていく戦略です。 士業やフリーランス、専門家など、「人に紐づく信頼」で仕事が成り立つ職種ではとくに重要です。
「この人なら信頼できる」「この人の発信はわかりやすい」という評価が、自然とビジネスチャンスを広げてくれます。
第6章:セルフブランディングを進める方法
セルフブランディングを効果的に行うには、以下の3ステップが基本です。
ステップ1:強みを明確にする
自分の専門性、経験、価値観などを棚卸しして「何を発信するか」を明確にします。
ステップ2:発信する
SNS、ブログ、動画、講演などの手段で情報を発信します。最初はフォロワー数より「誰に何を伝
えるか」が重要です。
ステップ3:一貫性を持たせる
発信内容やプロフィール、使用する写真や言葉遣いなどを統一することで、印象がブレず、信頼されやすくなります。
第7章:セルフブランディングの実践 ~「見た目」を変える~
セルフブランディングの中でも、「見た目」を変えることは非常にわかりやすく、効果が早く出やすい手法の一つです。 特に初対面の印象は「話す前に」決まるとも言われます。だからこそ、外見的な印象を整えること
は、ブランド力を高める非常に重要なステップです。 たとえば、見た目を変えるには、次のような方法があります:
①着るものを変える
②小道具を変える(メガネ・時計・バッグなど)
③体格を変える(ダイエット・姿勢改善など)
この中でも特に①と②は、比較的短期間かつ手軽に取り組めるため、最初の一歩として非常に効果的です。
私自身もまずは服装の見直しからセルフブランディングを始めました。 以前(いわゆる「ビフォアー」)は、紺系(黒に近い)のダークスーツにネイビーのネクタイという、ごく一般的で無難なスタイルでした。 おそらく多くの弁理士や士業の方がこのような服装をしていると思いますし、「信頼」「真面目さ」を伝えるには適したスタイルでもあります。 これに対して、現在(=「アフター」)は、写真をご覧のとおり、細い赤系ストライプが入った濃緑のジャケットに、光沢感のある赤いネクタイとチーフを合わせるスタイルに切り替えました。 全体的に少し華やかさと柔らかさが出ることで、以前よりも「話しかけやすい雰囲気ですね」と言われることが増えました。 この変化は、名刺交換の場や講演会など、第一印象が結果に直結する場面で大きな効果を実感しています。
とはいえ、自分だけで服装をガラリと変えるのは難しいものです。 そこで私が強くおすすめしたいのが、ファッションセンスのある方の助言をもらうことです。 私自身も、知人の紹介で服選びのアドバイスを受けたことで、ガラッと印象を変えることができました。
ちなみに、「ファッションセンスのある人ってどういう人?」というご質問をよくいただきます。 この点については、本日の講演終了後に個別にご案内いたしますので、ご興味のある方はぜひお気軽に声をかけてください。
第8章:セルフブランディングのデメリット・リスク
セルフブランディングも完璧ではありません。以下のようなリスクに注意が必要です。 柔軟性が高いが、一貫性の維持が難しい:テーマや方向性が頻繁に変わると、信頼を失いやすいです。 法的リスクは少ないが、炎上リスクがある:特にSNSでは、一言が誤解され、意図しない拡散を招くことがあります。 コストは低いが、継続的な発信に時間と労力がかかる:手間を惜しまず「続ける力」が必要です。 共感性は高いが、属人性が強い:個人に強く依存するため、代替や拡張が難しい場合もあります。 継続性に課題がある:本人が活動を停止すれば、ブランドも消える危険性があります。 初動の信頼構築は比較的容易:顔や声が見える分、短期間でのファン獲得が期待できます。
第9章:2つのブランディングの相乗効果
商標ブランディングとセルフブランディング。この2つはまったく別のもののようでいて、実は深く関わり合っています。 たとえば、会社のロゴや商品名がしっかり守られていても、その会社の社長が無名であれば、信頼を得るのに時間がかかります。
逆に、社長や担当者の発信が親しみやすく、信頼感がある場合には、商品やサービスにも好印象が波及します。 両者をバランスよく掛け合わせることで、「企業」と「個人」の信頼が相互に強化される。これが最強のブランディング戦略です。
第10章:すぐにできる実践アクション
最後に、講演を聞いてくださった皆さんが、明日からできるアクションをいくつかご紹介します。 ブランド名やロゴをチェックして、商標登録を視野に入れる 自分のSNSプロフィールを見直す(写真・肩書き・紹介文など) 見た目を変える第一歩として、服装や小道具を1つだけ変えてみる 誰か信頼できる人に「自分の印象」を聞いてみる こうした小さなアクションの積み重ねが、大きな成果につながっていきます。
第11章:2つのブランディングへの弁理士の関わり
ここまで、「商標ブランディング」と「セルフブランディング」の違いについてお話してきましたが、最後に、私自身の専門である弁理士という立場から、この2つのブランディングにどう関わっていけるかについて触れたいと思います。 まず、「商標ブランディング」の方は、まさに弁理士の本業中の本業といっていい分野です。 商標というのは、商品やサービスの“出どころ”を示すマークです。お客さんに「これはあの会社のものだな」と思ってもらえる、信頼の印のようなものですね。
また、商標制度というのは、商標の運用によって生じて蓄積される信頼、つまり企業の顔を守る制度です。 この商標を使って他社との差別化を図ったり、信用を積み上げていく――それが商標ブランディングの基本ですが、その裏側を支えるのが弁理士の仕事です。 具体的には、ネーミングやロゴが他人の商標とぶつからないかを調査したり、実際に特許庁に出願して登録を目指したり、登録後の更新管理や、権利を侵害されたときの対応など、ブランドを守るための法的なサポート全般を担っています。 つまり、商標ブランディングの現場において、弁理士は**制度面からブランドを支える“裏方のプロ”なんです。 一方で、「セルフブランディング」の方は、ちょっと毛色が違います。 こちらは、個人の経験や考え方、人柄やストーリーといった“人間らしさ”が軸になります。なので、法制度とはやや距離がある世界なんですね。 でも、最近ではセルフブランディングが進んでいく中で、個人の名前や肩書き、キャッチコピーを“商標登録”して保護したいというケースも増えてきました。
たとえば、「〇〇先生の△△メソッド」みたいなネーミングが広まって、それを誰かに真似されたら困る――そんな時に、「これ、商標登録にできませんか?」とご相談いただくこともあります。 この場合、弁理士は“個人の表現”を法的な権利として位置づけるサポート役になります。 つまり、セルフブランディングそのものには直接関わることは少ないですが、その発信が商業的に価値を持つようになった段階で、弁理士が登場するという形です。
まとめると、弁理士は商標ブランディングには深く関わる専門家でありつつも、セルフブランディングがビジネスとして花開いた時にも頼れる存在になれるということです。 結びに ブランディングとは、「自分や自社がどう見られたいか」を自ら設計することです。 そしてそれは、戦略として取り組めば、必ず成果が出る“技術”でもあります。 商標で企業の顔を守り、セルフブランディングで人としての信頼を築く。 この2つの力を正しく使い分け、掛け合わせていくことで、皆さんのビジネスや活動がより強く、
よりしなやかに成長していくことを願っています。 本日はご清聴、誠にありがとうございました。

御礼
委員会報告

親睦委員会 宮野 守 委員長 親睦旅行について 6月の旅行は熱海に決まりました。14日皆さんどうぞ、ご出席のほうよろしくお願いします。
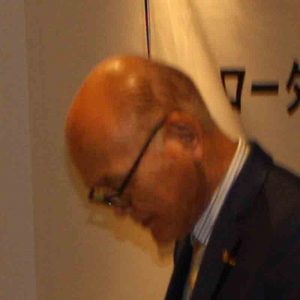
石井 弘会員 第13グループ野球部ということで、パンフレットを作り、いよいよスタートすることになりました。ウチのクラブからも何人か是非、参加をお願い致します。選手として参加を頂いてもよいですし、私のように球場に行って、発声をして発散をしていただいても結構です。年に一度、甲子園球場で、甲子園大会がありますので、家族で大阪に行って、楽しむ。野球の選手でありますから、そういう楽しみ方もあっていいかなと思いますので、どうぞ皆様、メンバーのほうに登録頂ければ、ありがたいと思います。
会長幹事にお願いをしたいのは、来年度ガバナー補佐として、ラーニングセミナー、IM、5クラブゴルフ大会がありますが、そろそろ準備委員会を設置して参ります。日にちも決まりましたので、今期の理事会のあと、各委員長さんの方々、お集まりいただいて、30分くらい、打ち合わせを随時していきたいと思います。


バッチ授与
マルチプル・ポール・ハリスフェロー(4回目)
福岡 秀実会員
お祝い披露

ニコニコ発表 浅野 実会員
天鐘 山本 衛会長
閉会